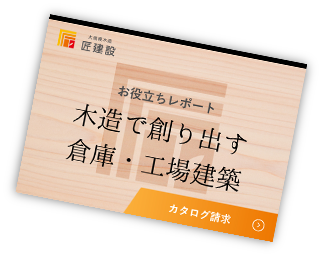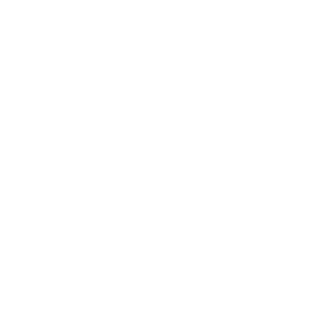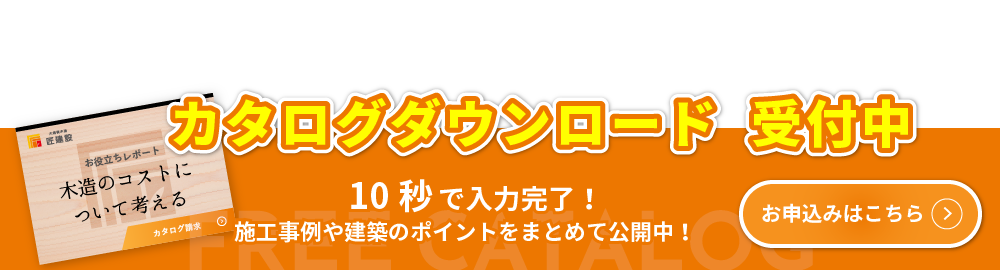みなさんこんにちは。高知県の大規模木造建築専門店の匠建設です。
「医療ケアの充実したナーシングホームを経営したいが、本当に儲かるのだろうか?」「ナーシングホームの経営を成功させるための具体的なポイントや、立ち上げの流れが知りたい」このような、ナーシングホームの経営に関する期待と不安をお持ちではないでしょうか。
超高齢社会の日本において、医療ニーズの高い高齢者を受け入れるナーシングホームの需要はますます高まっています。しかし、その経営は安定した収益が期待できる一方で、多くの課題やリスクも伴います。この記事では、ナーシングホーム経営の収益構造から、立ち上げに必要な費用と手順、そして事業を成功に導くための重要なポイントまで、大規模木造建築のプロの視点も交えながら、網羅的に解説していきます。
この記事を最後までお読みいただくことで、ナーシングホーム経営のリアルな実態が分かり、ご自身の事業計画を具体化するための確かな知識が身につきます。これからナーシングホームの経営を目指す事業者様は、ぜひ最後まで読んでみてください!
ナーシングホーム経営の基本|特養やサ高住との違い
ナーシングホームの経営を考える上で、まずはその定義と、他の介護施設との違いを正確に理解しておくことが重要です。
ナーシングホームとは?
ナーシングホームとは、看護師が常駐し、医療的ケアや看取りに対応できる体制を整えた高齢者向け施設の総称です。法律上の明確な定義はなく、多くは「住宅型有料老人ホーム」として届け出を行い、外部の「訪問看護ステーション」と連携、あるいは併設することで、手厚い看護サービスを提供しています。特別養護老人ホーム(特養)への入居が難しい、医療依存度の高い高齢者の受け皿として、その社会的ニーズは非常に高まっています。
他の介護施設との違い
このように、ナーシングホームは「介護」に加えて「看護・医療」に特化している点が、他の施設との大きな違いです。
参考:厚生労働省、介護・高齢者福祉(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index.html)
ナーシングホーム経営の収益性と課題
「ナーシングホームの経営は儲かるのか?」という問いに対して、答えは「綿密な計画と質の高い運営ができれば、安定した収益が期待できる」です。ここでは、その収益構造と、経営上の課題について解説します。
ナーシングホーム経営の収益構造
ナーシングホームの主な収益源は、以下の3つの柱で構成されます。
- 居住費・管理費: 入居者から受け取る家賃や共益費、水道光熱費などです。安定した収益の土台となります。
- 生活支援サービス費: 食事の提供や清掃、洗濯といった、介護保険外のサービス利用料です。
- 介護・看護サービス費: 併設・連携する訪問看護ステーションや訪問介護事業所が提供するサービスの対価として、介護保険や医療保険から支払われる報酬です。この部分が収益の大きな柱となります。
これらの収益を最大化するためには、施設の稼働率(入居率)をいかに高く維持するかが経営の最重要課題となります。
ナーシングホーム経営における3つの大きな課題
安定すれば収益性の高いナーシングホーム経営ですが、以下のような課題もあります。
- 人材の確保と定着: 看護師や介護士など、専門職スタッフの確保は年々難しくなっています。特に24時間体制で看護師を配置する場合、人件費の負担も大きくなります。働きやすい環境を整備し、スタッフの定着率を高めることが経営の安定に直結します。
- 他の施設との差別化: 近年、ナーシングホームと同様の機能を持つ施設が増えており、競争が激化しています。入居者に選ばれるためには、「看取りに強い」「認知症ケアに特化している」など、自施設の強みを明確にし、差別化を図る必要があります。
- 高い初期投資: 土地の取得や建物の建築、設備の導入には多額の初期投資が必要です。特に、スプリンクラーの設置義務など、法的な基準を満たすための建築コストは大きな負担となります。
ナーシングホーム経営の立ち上げから開設までの流れ
ナーシングホームの経営を始めるには、入念な準備と計画的なスケジュール管理が必要です。ここでは、立ち上げから開設までの大まかな流れを解説します。
- 法人設立と事業計画の策定: まずは、株式会社やNPO法人など、事業の運営母体となる法人を設立します。並行して、施設のコンセプト、サービス内容、収支計画などを盛り込んだ詳細な事業計画書を作成します。
- 資金調達: 事業計画書をもとに、自己資金に加えて日本政策金融公庫や福祉医療機構(WAM)などから融資を受け、必要な資金を調達します。
- 物件の確保と建築: 事業を行うための土地を選定し、建物を確保します。新築する場合、この段階で建築会社を選定し、設計を進めます。私が以前担当した高知県内のナーシングホームでは、木造建築にすることで建築コストを鉄骨造より15%ほど抑えつつ、木の温もりを活かした設計で、開所前に満室になった事例があります。
- 行政への届出・申請: 住宅型有料老人ホームとしての設置届や、訪問看護ステーションなどの指定申請を、管轄の都道府県や市町村に行います。
- 人材の採用と研修: 開設に向けて、管理者や看護師、介護士などのスタッフを採用し、理念やケア方針を共有するための研修を行います。
- 入居者の募集と開設: 建物が完成し、人員体制が整ったら、入居者の募集(営業活動)を開始し、晴れて開設となります。
ナーシングホーム経営を成功に導く木造建築という選択
ナーシングホーム経営における課題である「差別化」と「初期投資の抑制」、そして「人材の定着」を解決する鍵として、私たち匠建設は**「木造建築」**を強く推奨します。
木造の建物は、鉄骨造やRC造に比べて坪単価を大幅に(弊社実績にて約20%のコストダウンが可能)抑えられるため、初期投資の削減に直接的に貢献します。さらに、木の持つ温もりや優れた調湿・断熱性は、入居者にとって快適で健康的な住環境を提供し、他の施設との明確な差別化に繋がります。そして、そのような居心地の良い空間は、働くスタッフにとっても精神的な安らぎを与え、離職率の低下、つまり人材の定着にも良い影響をもたらします。
介護施設の費用について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
まとめ
ナーシングホームの経営は、高い社会的ニーズを背景に、安定した収益が期待できる魅力的な事業です。しかしその一方で、人材確保や施設間の競争、多額の初期投資といった課題も存在します。
これらの課題を乗り越え、経営を成功させるためには、明確な事業計画と質の高いケアはもちろんのこと、事業の器となる「建物」そのものが非常に重要な役割を果たします。木造建築は、コストを抑えながらも、入居者とスタッフの双方にとって快適で魅力的な環境を創出できる、ナーシングホームに最適な構造です。
私たち匠建設は、高知県で大規模木造建築を専門に手掛けてきた実績とノウハウがあります。ナーシングホームの経営をご検討の際は、事業計画の段階から、コストと品質、そして理念を形にする建築プランまで、ぜひ一度私たちにご相談ください。












-300x169.jpg)